老後2000万円問題や年金支給年齢の引き上げなど、定年が現実的になる50代にとっては心配なニュースが多い状況です。
実際、老後資金への不安解消や退職後の生活費確保を目的に、投資へ関心を持つ方も増えています。
しかし、「50代から投資しても遅いのではないか」「投資って何をすればいいのか分からない」と感じている方もいるでしょう。
本記事では、50代からでも資産をどれくらい増やせるかやどのような投資先があるのかについて、初心者にもわかりやすく解説します。
この記事を読めば、50代からでも投資を始めるべき理由や自分に合った投資が分かるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。
50代からの投資が遅くない理由3つ
50代から投資を始めたとしても、老後に必要なお金は貯まらないと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本章では50代からでも投資は遅くない理由3選について解説します。
これらの理由を知っておくことで、老後の備えは50代からでも間に合うと理解可能です。
それぞれの内容について、以下で順番に見ていきましょう。
子どもにかかるお金が減る
50代になると子どもが社会人になり、教育費がかからなくなります。
ほかにも毎月かかっていた塾代・交通費・お小遣いなどが不要になるでしょう。
その分を投資に回すことで、無理なく老後に備えることが可能です。
少し余裕ができる世代だからこそ、投資を始めるには適した時期になります。
退職前に投資の知識を学べる
50代の場合、退職前に投資を始めることをおすすめします。
なぜなら、退職金などのまとまったお金をいきなり投資に回すのはリスクが高いからです。
始めは順調に株価も上がってましたが、突然の世界同時株安で資金繰りが悪化し倒産してしまいました。
こうなると、老後のために投資した1000万円はただの紙切れになってしまいます。
このように、知識や経験がまったくない状態で投資を始めるのは危険です。
まだ収入を得ている50代から投資を始れば、失敗したとしてもリカバリーすることができるでしょう。
いきなり大きな金額を運用する前に投資の経験を積むことで、失敗のリスクを軽減することが可能です。
退職後の生活が具体的に検討できる
投資を始めるときは、老後にどれくらいのお金が必要かを把握しなければなりません。
なぜなら、その金額を理解してないと資産運用の計画が立てれないからです。
また、実際に受け取る年金や退職金の額などが、正確に分かるようにもなるでしょう。
このように、退職後の生活がはっきり見えてくるからこそ、資産運用が始めやすくなるのです。
50代におすすめの投資3つ
一言で投資といっても、どんな種類があるか分からない方もいらっしゃるでしょう。
そこで本章では50代におすすめの投資3選を紹介します。
投資の種類を知ることで、自分にあった投資プランの検討が可能です。
それぞれの投資先について、以下で順番に見ていきましょう。
株式投資
株式投資とは、企業が発行する「株式」を売買または保有することで利益を得る手法です。
株式投資で得る利益には、以下の3つがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 売買差益 | 株を安く買って高く売れたときの差額で得る利益 |
| 配当金 | 一定期間保有することで得られる企業の利益の分配金 |
| 株主優待 | 企業の独自商品や金券などがもらえる |
売買差益は、株価が上がると儲かる可能性は高まりますが、下がると損失リスクも高くなります。
一方、配当金や株主優待は保有する限りメリットを受けることが可能です。
どの種類の利益を選ぶかは、運用資金の金額やリスクの許容範囲などから検討しなければなりません。
つぎに株式投資のメリット・デメリットを紹介します。
メリットとデメリットは両方把握して投資手段を選択しましょう。
- 株価が上がると高いリターンが得られる
- 企業からの配当金や株主優待をもらえる銘柄もある
- 株主は会社の意思決定に参加する権利がある
その分リターンも大きくなりますが、情報収集や売買のタイミングなど個人の知識と経験が必要な投資手段になります。
小額でおこなう分には魅力的ですが、メインの投資先とするにはリスクが大きいでしょう。
投資信託
投資信託とは、投資のプロに資産運用を任せる金融商品です。
そこで発生した運用益が出資した金額に応じて分配されるという仕組みです。
運用のプロに任せるため、情報収集や取引に時間を割かれることがありません。
つぎに投資信託のメリット・デメリットを紹介します。
投資のプロに任せるとはいえデメリットもあるので、許容できるリスクなのか確認は必要です。
- 小額から投資することができる
- 値動きのチェックや情報収集をプロに任せられる
- 分散投資が基本なので破綻リスクが少ない
投資信託は株式投資ほどリスクが高くありません。
投資のプロに任せることで、個人の投資スキルが必要なくストレスもかからないでしょう。
どれくらいのリスクを許容できるかで投資額を判断しましょう。
債権投資
債券投資は、債権を購入してから償還日に元本を返却してもらうまで利子を得続ける手法です。
債権は国や地方自治体、企業などが発行する借用証書で、投資家から資金を調達する目的で発行されます。
そして償還日には元本を全額返す仕組みになっており、株式などに比べてリスクが少ない投資です。
代表的なものに「国債」「地方債」「社債」「外国債」などがあります。
つぎに債券投資のメリット・デメリットを紹介します。
リスクが少ないとはいえデメリットもきちんと把握しておきましょう。
- 定期的に利息がもらえる
- 償還日に全額返却される(信用リスクを除く)
- 途中で売却して換金できる
- 運用の手間がかからない
紹介した3つの中ではリスクが一番低い投資手段です。
その分受け取るリターンの比率も低くなります。
資金力があり安定した利益を確保したい場合に有効な投資手法です。
50代の資産運用で活用したい制度
国が投資を推奨するために、投資で得た利益を非課税にするお得な制度をご存知でしょうか。
誰でも投資をするからには少しでも利益を得たいものです。
そこで本章では、50代の資産運用で活用したいお得な制度を2つ紹介します。
この記事を読めば、税金が優遇された制度が分かり、資産運用でお得に活用することができます。
それぞれの制度の詳細について、以下で順番に見ていきましょう。
NISA(少額投資非課税制度)
通常、投資で得た運用益には20%ほどの税金がかかります。
これをNISA口座で運用すると、いくら利益がでても非課税になるという税制優遇制度です。
一般NISAは年間120万円が上限で最長5年間までが非課税となり、株式や投資信託などさまざまな金融商品に投資することが可能です。
つみたてNISAの非課税枠は年間40万円で期間は20年となっており、投資可能な商品は投資信託に限られています。
このお得な制度が、2023年度の改正で2024年よりさらにお得な新NISA制度に変わりました。
| 新NISA制度 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 投資対象商品 | 長期・積立・分散に適した 金融庁が厳選した投資信託 | 株式、ETFなど |
ジュニアNISAが廃止され一般NISAが成長投資枠、つみたてNISAがつみたて投資枠に名称が変わりました。
また、投資枠も増額され非課税期間も無制限となり、積極的に活用したいお得な制度になってます。
ここでNISAのメリット・デメリットを以下にまとめてみました。
- 投資の利益が非課税
- 少額から投資できる
- 投資初心者でも始めやすい
- 投資商品が選びやすい
国が厳選した比較的安全な商品を選べ、少額から始めることで投資に慣れることもできます。
また、非課税になる金額に上限はありますが初心者にはメリットの多い制度です。
元本割れに注意しつつ積極的に活用しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、老後の資金作りを目的とした私的年金制度のことです。
公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けることができるので、年金で不足する分を補うことができます。
また、給付額は運用実績によって決まり、原則60歳以降に年金または一時金として受け取ることができます。
ここでiDeCoのメリット・デメリットを以下にまとめてみました。
- 掛け金が全額所得控除の対象
- 利息や運用益は非課税
- 将来受け取る年金・一時金ともに税制優遇される
毎月の掛け金が全額所得控除になり、利息や運用益も非課税となるメリットが多い制度です。
また、50代から始めると最低10年の加入期間が必要なため、受取りできる時期には注意が必要です。
投資シミュレーション

金融庁の公式ページで「毎月の積立額」「想定利回り」「期間」を入力すると、概算の運用益がわかります。
資産計画を立てる上で参考にしてください。
50代の投資で注意すべき点
投資を始めるならできるだけリスクを減らしたいと考える方も多いでしょう。
そこで本章では、50代が投資を始める上で注意すべき点を3つ紹介します。
この記事を読めば、どのようにしてリスクを抑え安全に資産を運用できるかを知ることが可能です。
それぞれの注意点について、以下で順番に見ていきましょう。
老後に必要な資金を明確にする
投資を始めるまえに老後の収入と支出を把握し、いつまでにどれくらい貯めるのかを決めておきましょう。
なぜなら目標金額と達成時期を設定することで、投資計画が立てやすくなり適切なリスク管理ができるからです。
たとえば
- 年金は夫婦でいくら受け取れるのか
- 退職金はいくら受け取れるのか
- 定年後の生活費はどれくらい必要か
- 住居にかかる費用はどれくらいか
- 生活費以外の支出はどれくらいか
など、できるだけ詳しく書き出してみましょう。
そうすることで、いくらまでならリスクを抑えて投資可能なのか算出することができ、安全な投資計画を立てることができます。
投資先を分散する
50代からの投資は1つの投資先に集中投資するより、複数の金融商品に分散して投資するようにしましょう。
その理由は、1つの投資先で損失を出してしまうと資産が大きく減少し、大切な老後資金を失う可能性が高くなるからです。
しかし、50代からはその期間が短く、取り返そうとする焦りからハイリスクな商品に手をだしたくなるのです。
そして損失が拡大する負の連鎖によって、すべてを失うことになってしまいます。
そのため、投資先はできるだけ分散させ損失リスクを極力小さくすることをおすすめします。
ハイリスク・ハイリターンの投資はやめる
先ほど申したように、運用期間が短い50代からの投資は焦って結果を出そうとする方が多くいらっしゃいます。
短期間でハイリターンを得る投資を、非常に魅力的に感じる方もおられるでしょう。
老後の生活を考えて投資しているのに、大きな利益を狙った結果すべてを失うことは本末転倒です。
50代からの投資は許容できるリスクの金融商品を選択し、運用するようにしましょう。
50代からでも投資を始めて老後に備えましょう
この記事では、50代から投資を始めても老後の資産形成に間に合うことを解説しました。
投資は怖いと感じている方も、少額で始めて慣れてから投資額を増やせば損失リスクを抑えることも可能です。
しかも、投資に慣れることで自分に合った投資先やリスク管理などが分かるようにもなります。
もう遅いとあきらめず、まずは始めることが理想とする老後のスタート地点です。
老後に必要な資金計画を立て、許容できるリスクの範囲で資産を運用し豊かな老後を目指しましょう。


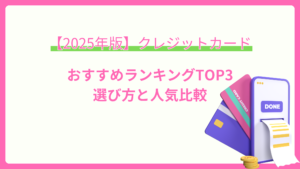
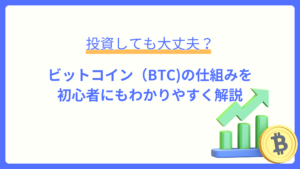
コメント